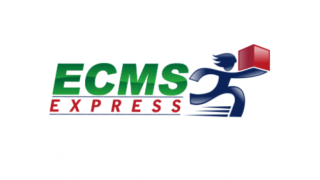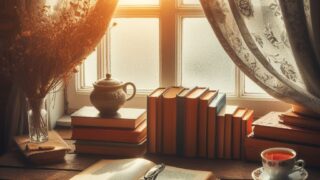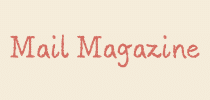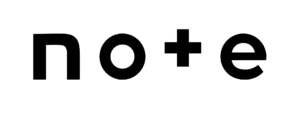目次
1歳〜2歳の言葉の発達への不安は当然です
「ウチの子、なかなか喋らないけど大丈夫かな…」
そんな風に不安になること、ありますよね。
言葉の発育が遅いのでは?と、つい周囲の子と比べてしまう。
でも安心してください。
1歳〜2歳の時期なら、まだまだ話せなくて当然です。
個人差も大きいこの時期、大切なのは焦らず、そしてあきらめずに関わり続けること。
話せなくても、子どもはちゃんと聞いています
「話しても返事がないから」と、話しかけるのをやめてしまうことはありませんか?
でも、子どもはちゃんと聞いています。
大人が話す言葉、声のトーン、表情、ぜんぶ吸収しているんです。
一方的に情報を受け取るだけの動画やテレビばかりでは、子どもの”言葉のタネ”は育ちにくくなります。
そして…スマホを見てばかりの親。
子どもはそんな姿も、ちゃんと見て真似しています。
孔子の教え「学而時習之」が示す学習の本質
ここで、約2500年前の孔子の言葉を思い出してみましょう。
論語の冒頭に「学而時習之、不亦説乎」(学びて時に之を習う、亦説(よろこ)ばしからずや)という有名な言葉があります。
これは「学んだことを折に触れて復習し実践すれば、それは喜ばしいことではないか」という意味です。
孔子は、真の学びとは単に知識を詰め込むことではなく、繰り返し実践することで身につけていくものだと説いています。
子どもの言葉の発達も、まさにこの教えの通りです。
聞いて、真似て、繰り返すことで、言葉は子どもの中に根づいていくのです。
「マネる」から始まる学びのプロセス
子どもは、大人の真似をしながら世界を学んでいきます。
言葉も、しぐさも、感情の表現も──すべてはマネから始まるんです。
だからこそ、日常の中でしっかりと向き合って言葉を交わすことが大切。
そのための最強のツールが、「絵本の読み聞かせ」です。
絵本は”ことばの教科書”
膝の上にちょこんと座らせて、親子で同じ絵を見ながら、言葉を交わす。
読み聞かせは、安心感を生み、語彙を育て、想像力を伸ばします。
親の声の抑揚や表情を感じながら、子どもは「ことば」の世界を広げていくのです。
兄弟姉妹のいるご家庭では、下の子のほうが言葉が早く育つことがよくあります。
それも、日常的に「おしゃべりのモデル」が近くにいるからです。
「学ぶ」は「マネる」から生まれる革新
「学ぶ」という言葉は、「真似ぶ」から来ているとも言われます。
たとえば…
Appleのスティーブ・ジョブズが生み出したiPodの原点には、SONYのウォークマンがありました。
さらにそのSONYも、アメリカ製品を模倣し、工夫と改良を重ねて生まれた製品でした。
つまり、模倣→工夫→進化というプロセスを経て、新しいものが生まれていくのです。
実体験から学んだ「マネの力」
そんな「マネの力」を実感した、ある日の出来事をお話しします。
娘が孫に聞きました。
「おばあちゃんのお名前は?」
──「〇〇ちゃん!」
「じゃあ、ママのお名前は?」
──「〇〇ちゃん!」
そして最後に…
「ジージのお名前は?」と聞くと……
孫は少し考えてから、こう答えたのです。
「オッサン!」
家族中が大爆笑。
実は、娘も妻も、普段私のことを「オッサン」と呼んでいたんです。
孫はそれをそのまま覚えて、インプットしていたのでしょう。
子どもの言葉の発達を促す3つのポイント
1. 日常会話を大切にする
スマホを見ながらではなく、目を見て話しかけることで、子どもは言葉の意味と感情を一緒に学びます。
2. 絵本の読み聞かせを習慣化する
親の膝の上で聞く言葉は、子どもの心に深く刻まれます。毎日少しずつでも続けることが大切です。
3. 真似されても良い言動を心がける
子どもは大人の姿を見て、聞いて、真似をして育っていきます。私たち大人の普段の言動や態度に責任を持つべきです。
まとめ:親の関わりが子どもの未来を育む
孔子の教えの通り、学びは繰り返しの実践から生まれます。
子どもの言葉の発達も同じで、日々の親子の関わりの中で、真似を通して育っていくのです。
笑えるエピソードの裏に、深い学びがありました。
「学ぶは、真似ぶ」── 子どもは、あなたの”まねび人”です。
どんな姿を見せていきますか?
✨ 変化のきっかけを探しているあなたへ
道徳の名言・格言から学ぶ
子育てに活かせる徳育のエッセンス
🎯 毎日負担なく、簡単で手軽に
🎯 短時間で今からでもできる
🎯 小さなチャレンジから大きな変化へ
体験することで気づく、感じられる
そんなコンテンツを様々な形でお届け。
あなたの「明るい未来」を一緒に見つけませんか?
メルマガ では、今からできる小さなチャレンジの提案をしています。
詳しくは下記のリンクまで